小規模宅地等の特例
相続した宅土地等が一定の要件に該当する場合、その土地の評価額を一定面積を上限に50%もしくは80%減額するという特例を、小規模宅地等の特例と言います。
これはあくまでも相続税の計算に使用する土地の評価額が最大80%安くなるのであって、相続税が最大80%安くなるのではありません。
なお大前提として、小規模宅地等の特例を使うには、相続税の申告期限である「相続開始から10ヵ月以内」に、遺産分割協議を完了させておく必要があります。
限度面積と評価額の減額率は、相続した土地が誰にどのように使われていたかによって変わります。
3種類の限度面積と減額率
| 相続する土地の区分 | 限度面積 | 減額率 |
|---|---|---|
| ① 特定居住用宅地等 (自宅用に使っていた土地等) | 330㎡ | 80% |
| ② 特定事業用宅地等 (事業用に使っていた土地等) | 400㎡ | 80% |
| ③ 貸付事業用宅地等 (賃貸事業に使っていた土地等) | 200㎡ | 50% |
①特定居住用宅地等:被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が居住用に使っていた土地。
②特定事業用宅地等:被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族の事業で使っていた土地。
③貸付事業用宅地等:被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が、第三者に貸したり賃貸アパートなどを建てていた土地。
軽減効果の計算例
例えば「特定居住用宅地等」に該当し、500㎡で相続税評価額1億円(20万円/㎡)の土地を相続することになった場合、土地の330㎡までの部分の評価額を80%減額し、残り170㎡部分はそのままの評価額とし、2つの額を足すことで土地の評価額を求めます。
・20万円/㎡ ×330㎡ × (1 – 0.8) + 20万円/㎡ × 170㎡
=4,720万円 (5,280万円の減額)
1億円を相続した場合の相続税=2,300万円
4,720万円を相続した場合の相続税=744万円
★軽減できた相続税額=1,556万円
相続税の税率と計算方法はこちら▼
また、前項①と②に該当する土地を複数相続する場合は、特例の併用が可能です。(上限面積は合計730㎡)
土地が複数で上限面積よりも大きな場合は、特例の恩恵を受けやすい評価額の大きな土地から優先的に特例を適用させていくとよいでしょう。
なお、①~③の特例を利用するには、その土地の利用状況、相続人が、それぞれ以下のような細かな条件に該当する必要があります。
■特定居住用宅地等の要件
小規模宅地等の80%軽減は原則として、被相続人と同居ししていた親族が相続をした場合に限り利用できる特例ですが、被相続人と別居していたり生計を一にしていない親族が相続した場合でも、要件を満たせば同様に宅地評価額の80%軽減が利用できる『家なき子特例』という特例もあるため、下記要件はその特例の要件も含めたものにしてあります。
①土地の要件
被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が居住用に使っていた土地。
②相続人の要件(下記いずれかに該当すること)
【土地が被相続人の居住の用に供されていた場合】
1.配偶者が取得した場合。
2.被相続人と同居していた親族が取得し、相続税の申告期限まで引き続き居住している場合。
3.被相続人に配偶者や同居していた親族がいない場合、相続開始前3年以内に、相続人本人または相続人の配偶者が所有する家屋(つまり持ち家)に居住したことがない親族が取得した場合。
【被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合】
4.配偶者が取得した場合。
5.被相続人と生計を一にしていた親族が取得し、相続開始前から相続税申告期限まで自己の居住の用に供している場合。
!適用除外要件!
①配偶者が取得した場合を除き、相続税の申告期限までその土地を所有していないと適用外に。
②下記の者については適用除外。
1.相続開始前3年以内に、その相続した者の三親等内の親族又はその者と特別関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者。
2.相続開始時において居住の用に供していた家屋を、過去に所有していたことがある者。
※②は平成30年に厳格化された「家なき子特例」の要件より。
分かりやすいケースとして、相続人要件の⑤を一例に挙げてみると、
親が上京する子供のために区分所有マンションを親名義で買って住ませ、仕送りによって生活を支えていた場合、親が亡くなる前から亡くなった後の相続税申告期限まで子供がそのマンションに住み続けていれば、そのマンションの土地の評価額について80%減額の特例を受けられることになります。
■特定事業用宅地等の要件
①土地の要件
被相続人または、被相続人と生計を一にしていた親族が、相続直前において事業で使っていた土地。
※不動産賃貸業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業は対象外。
②相続人の要件(下記いずれかに該当すること)
1.被相続人の事業の用に供されていた場合で、被相続人の事業を引き継ぎ、相続税の申告期限まで引き続きその事業を営んでいる親族が取得した場合。
2.被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた場合で、取得者が相続開始前から相続税申告期限まで引き続きその事業を営んでいる場合。
!適用除外要件!
①相続税の申告期限までその土地を所有していないと適用外に。
②相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地は適用外。
ただし、当該宅地の上で事業に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地の相続時の価額の15%以上である場合は特例が適用可能。
■貸付事業用宅地等の要件
①土地の要件
被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が、相続直前において第三者に貸したり賃貸アパート事業などで使っていた土地。
※不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業に限る。
②相続人の要件(下記いずれかに該当すること)
1.被相続人の不動産貸付事業の用に供されていた場合で、被相続人の不動産貸付事業を引き継ぎ、相続税の申告期限まで引き続きその貸付事業を営んでいる親族が取得した場合。
2.被相続人と生計を一にしていた親族の不動産貸付事業の用に供されていた場合で、その生計を一にしていた親族が取得し、相続開始前から相続税申告期限まで引き続きその貸付事業を営んでいる場合。
!適用除外要件!
①相続税の申告期限までその土地を所有していないと適用外に。
②相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は適用外。
ただし、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のものをいいます。以下同じです。)を行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供された宅地等については特例の適用が可能。

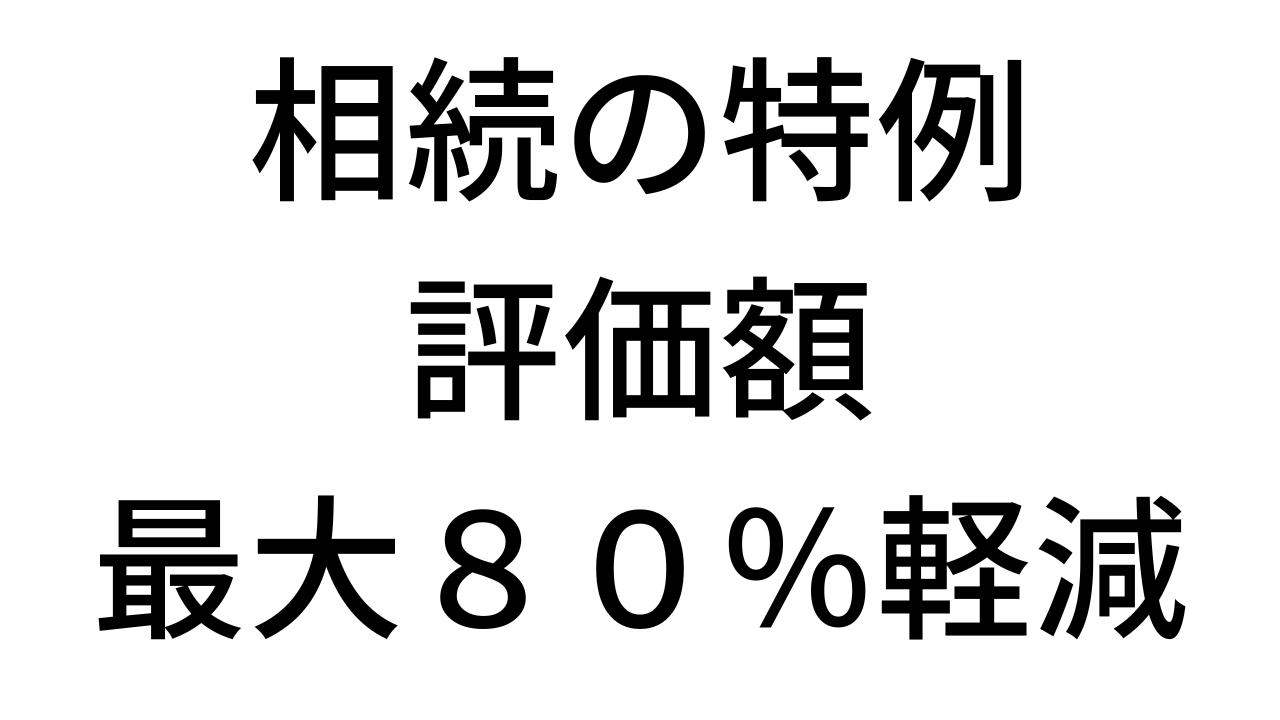

コメント