2026年4月1日から、不動産の所有者が「住所」や「氏名」を変更した場合、変更から2年以内に登記の変更を申請することが義務となります。
これまで住所や氏名の変更登記は任意だったため、引っ越しや結婚・離婚などで変更をしていない方も多かったと思います。
しかし今後は「義務」となり、正当な理由なく放置していると「5万円以下の過料(罰金)」が科される可能性があります。
つまり、マイホームでも、投資用のマンションでも、「登記上の情報を最新に保つこと」が必須になったということです。
◆ 義務付けられた背景について
この制度が導入された背景には、「所有者不明土地問題」があります。
国土交通省の調査によると、所有者が分からない土地の面積は九州本島の面積を上回るとも言われています。
相続登記をしていなかったり、所有者が転居・死亡して連絡が取れなくなったりといったケースが多く、これが公共事業や防災対策を進めるうえで大きな障害になっていました。
住所や氏名の変更登記が義務化されることで、登記簿上の情報がより正確に保たれ、行政や民間での土地取引の円滑化にもつながると期待されています。
◆ 住所変更登記の方法と費用について
住所変更登記は、司法書士に依頼して行うこともできますし、自分で行うことも可能です。
自分で行う場合は、法務局に「登記申請書」と「変更を証明する書類(住民票や戸籍附票など)」を提出します。
「登記」と聞くと「難しそう」と身構えてしまいそうですが、申請に必要な書類は少なく、登録免許税は不動産1件につき1,000円程度と費用も比較的安く済みます。
なお、司法書士に依頼する場合は、手数料を含めて1件あたり数千円〜1万円前後が目安です。
手間をかけたくない方や、売却前の住所変更登記で失敗ができない場合は専門家に任せるのもよいですし、時間がかけられる人は勉強がてら自身で申請をしてみるのもよいでしょう。
◆ スマート変更登記の紹介
今回の制度に合わせて、「スマート変更登記」という新しい仕組みもスタートします。
これは、マイナンバーカードを使って「住民基本台帳の変更情報」を法務局に自動で連携できるようにするものです。
つまり、住所変更を市区町村に届け出ると、その情報を基に職権で登記の変更が行われる、という仕組みです。
すべてが自動で完了するわけではありませんが、従来のように登記簿の変更を自分で申請する手間を大きく減らせる制度です。
今後はデジタル庁・法務省・自治体が連携し、順次この仕組みが広がっていく見込みです。
◆スマート変更登記の利用「検索用情報の申出」
スマート変更登記を利用するためには、まず「検索用情報の申出」という手続きが必要です。
これは、自分が所有している不動産の登記をマイナンバーと紐づけるための申出で、対象者は不動産の所有者本人です。
手続きは法務局で行うほか、オンラインでも申出可能です。
申出をしておくと、自治体の住民情報と登記情報が連携され、将来的に住所変更登記が自動的に処理されるようになります。
一度登録しておけば、引っ越しのたびに登記を自分で申請する手間がなくなる、というわけです。
◆スマート変更登記の問題点について
一方で、この制度には注意点もあります。
たとえば、DV被害者やストーカー被害者など、住所を秘匿する必要がある人の場合、住民票上の住所を登記に自動反映させるとリスクが生じるおそれがあります。
そのため、こうした事情がある場合には、スマート変更登記の対象から除外申請を行うことができます。
また、マイナンバーと登記情報を連携させることに抵抗を感じる方もいるかもしれません。
プライバシー保護の観点からも、制度の運用では今後も議論が続くとみられています。
◆まとめ
これまで住所変更登記をしていなかった人も、2026年4月以降は「義務」となります。
違反したからといってすぐに過料が科されるわけではありませんが、登記簿の情報を正しく保つことは、自分の財産を守ることにもつながります。
今のうちから、自分の所有不動産の登記情報を一度確認し、住所や氏名が古いままになっていないかをチェックしておきましょう。
また、スマート変更登記の仕組みをうまく活用することで、将来的な手間を減らすことも可能です。
不動産の管理は「持っているだけ」ではなく、「情報を正しく維持すること」も大切な時代になってきています。



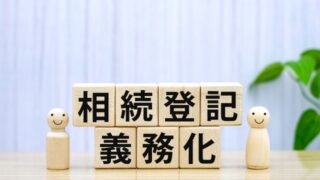
コメント